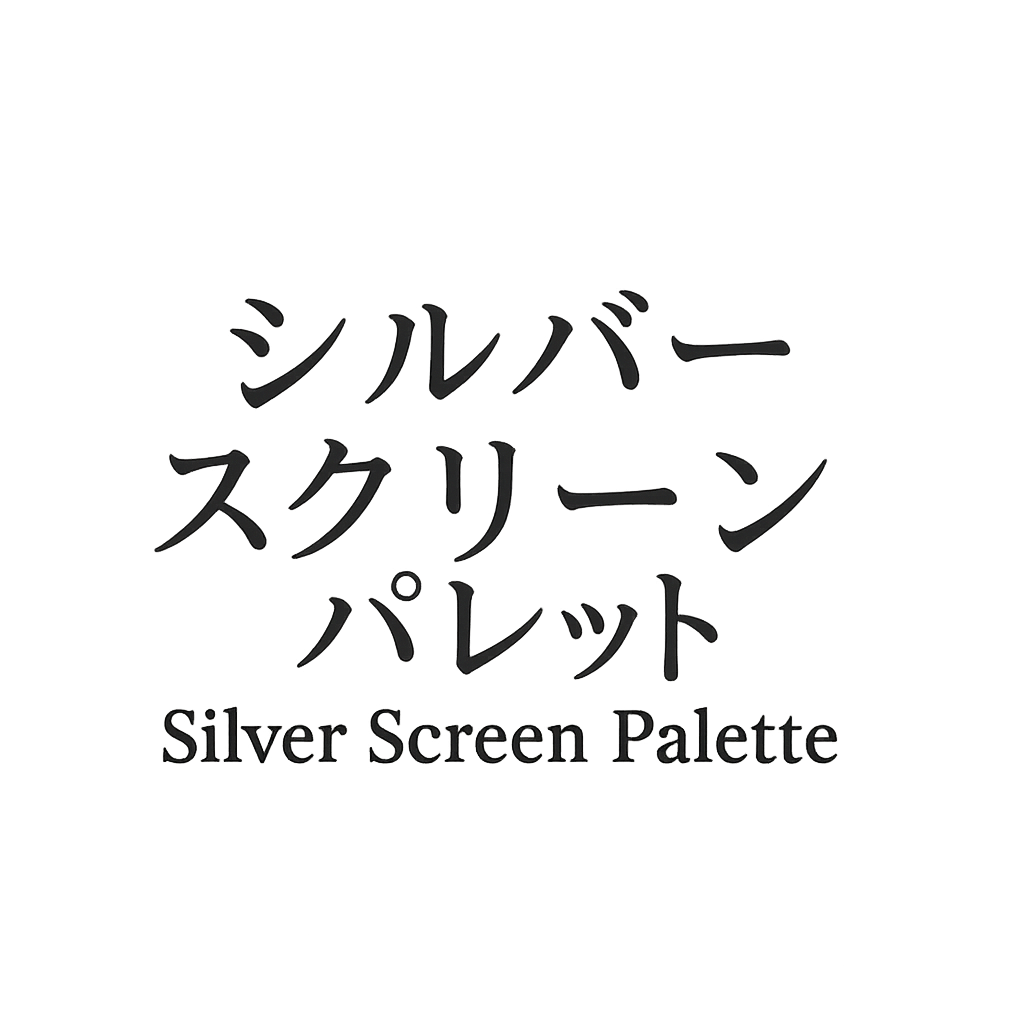映画 赦し レビュー 第10章:社会の無関心と「止められなかった責任」──誰もが問われる罪【ネタバレ注意】

【ネタバレを含みます】
本記事では、映画『赦し』の登場人物や象徴的なシーンについて触れています。物語の印象を大切にされたい方は、鑑賞後にご覧いただくことをおすすめいたします。
出典:YouTube / A FILM BY ANSHUL CHAUHAN 公式チャンネル
第10章:社会の無関心と「止められなかった責任」──誰もが問われる罪
語られたときには、もう手遅れだった過去。
それがいじめという形で、夏菜の口から静かに明かされるのは、物語の終盤に差しかかってからのことです。けれども、そこで私たちが抱くのは、単純な同情ではなく、むしろ言葉を失うような戸惑い──どうして、誰も止められなかったのだろうという、重い問いかけなのかもしれません。
前の章を読む:
▶第9章:語られた言葉の空虚──形式と“赦し”のすれ違い
はじめから読む:
▶ 第1章:序章──映画『赦し』の核心へと導く視点
語られたいじめの記憶──その背景にあった孤独の軌跡
再審の場で、夏菜が告白したいじめの記憶は、単なる背景説明ではありません。
それは、彼女が殺人という行為に至るまでの孤独な軌跡を照らし出すものでした。クラスメイトからの無視や嘲笑、教師からの軽視──その連鎖が彼女の心を追い詰め、やがて取り返しのつかない行動へと結びついていったのです。

この場面を見ていると、私たちは観客として、ただ状況を追体験するだけでは済まされません。「なぜ、そこに手を差し伸べる者がいなかったのか」という問いが、胸の奥に静かに突き刺さるのです。夏菜の孤独は、単に彼女個人の問題ではなく、社会全体の無関心と制度の限界が生んだ結果でもあることが、強く印象に残ります。
傍観と沈黙の罪──“何もしなかった”という暴力
加害の中心にいた者たちだけでなく、取り巻きや傍観者、あるいは「空気に流された」と語る同級生たちも、なぜ止めなかったのか、なぜ逃げなかったのか。そうした“何もしなかった存在”こそが、この映画において最も冷たく映る瞬間があります。
悪意がなかったという言い訳は、どこかで恐ろしい響きを帯びます。悪意の不在が、結果として他者を追い詰め、取り返しのつかない結末を招いたと考えれば、傍観そのものもまた、ひとつの暴力となるのです。

見て見ぬふりをした大人たち──沈黙の連鎖と制度の機能不全
さらに重要なのは、大人たちの沈黙です。教師や学校関係者は、本当に何も知らなかったのでしょうか。それとも、「関わりたくなかった」「騒ぎを大きくしたくなかった」という理屈で、見て見ぬふりをしたのでしょうか。
映画は、この問いに対して明確な答えを示しません。むしろ、語られなかった部分が観客自身の想像に委ねられることで、「問いの余白」を残します。その余白こそ、観る者に対して強い倫理的な責任を突きつける構造となっているのです。

“他人事”ではない──観客としての責任
視点をさらに広げれば、社会全体の機能不全も浮かび上がります。制度も支援も、声を上げる仕組みも──誰一人、彼女をすくい上げられなかったという事実。その連鎖の末に、あの夜の事件が起きたのだとすれば、この物語は決して“他人事”では済まされません。
『赦し』は、単純な善悪で裁く物語ではありません。むしろ、「もし誰かが手を差し伸べていれば」という小さな仮定が、どれだけの未来を変え得たか──そんな静かな問いかけを通じて、観る者一人ひとりに責任の所在を問う作品なのです。
沈黙の暴力──観客自身を問う視点
もしも沈黙が暴力の温床になるとしたら、この映画の中には登場しない「私たち観客」の沈黙こそが、最も根深い問いを孕んでいるのかもしれません。見ているだけで何もしなかったこと、語られることを避け、無関心を装ったこと──その小さな沈黙の積み重ねが、現実世界では取り返しのつかない結果につながる可能性があります。
映画は、あくまで物語として過去を描きつつも、私たちに“目を背けることの罪”を静かに問いかけます。そして、責任を誰か他人に押しつけるのではなく、社会全体が共有すべき問題として提示するのです。
次章予告
次章では、「語ること」と「酔うこと」が映し出す、人の弱さとずるさに光をあてます。
“赦し”を語りながら、語りきれないものを抱える人々──その沈黙の奥にある、ほんとうの姿とは何か。私たちは、言葉の裏に潜む感情と向き合う必要があるでしょう。
次の章を読む:
▶ 第11章:演出としての“弱さ”──語り、酔い、立ち位置の曖昧さ