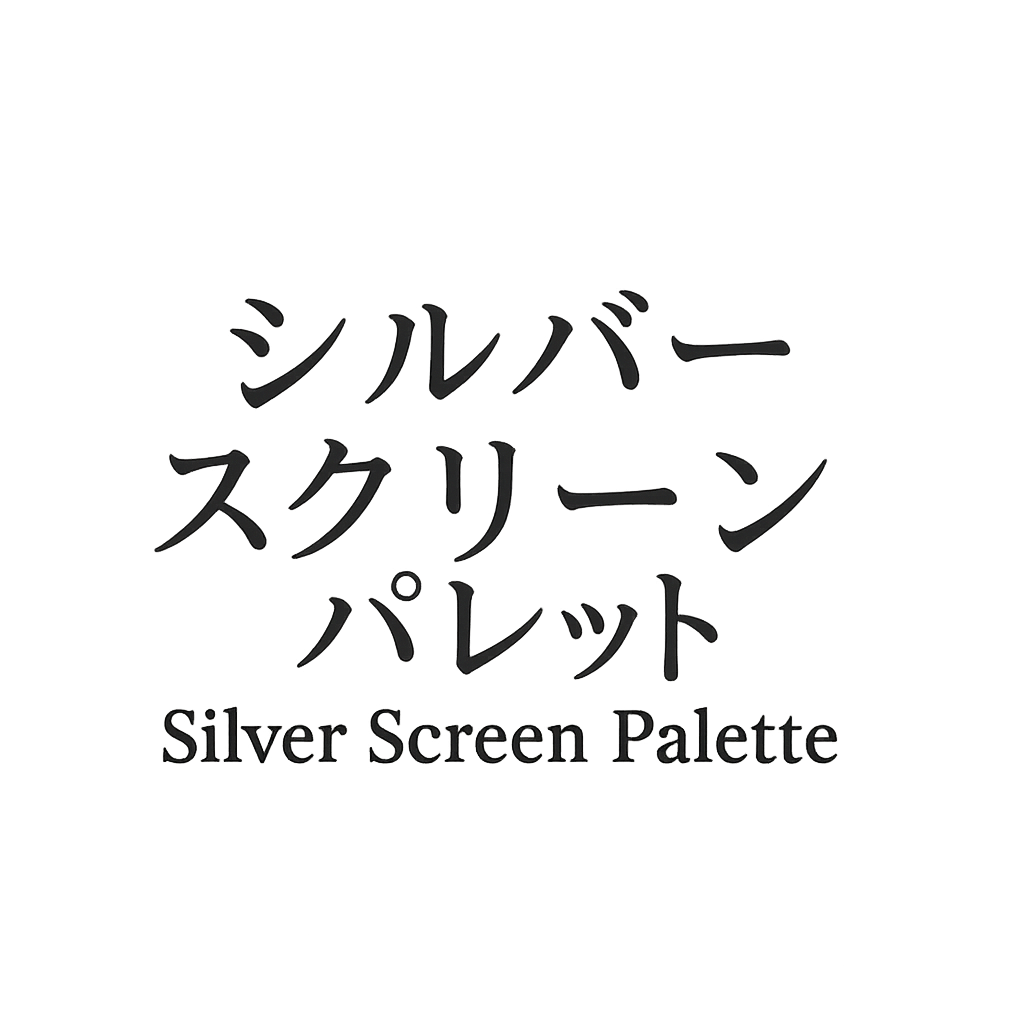映画 赦し レビュー 第11章:演出としての“弱さ”──語り、酔い、立ち位置の曖昧さ【ネタバレ注意】

【ネタバレを含みます】
本記事では、映画『赦し』の登場人物や象徴的なシーンについて触れています。物語の印象を大切にされたい方は、鑑賞後にご覧いただくことをおすすめいたします。
出典:YouTube / A FILM BY ANSHUL CHAUHAN 公式チャンネル
第11章:演出としての“弱さ”──語り、酔い、立ち位置の曖昧さ
“赦し”とは、ただ与えられるものではなく、時に語ることで、時に沈黙の中で、じわりと輪郭を浮かび上がらせるものなのかもしれません。
けれど、その語りが、誰かのためではなく、自分のためだけの行為だとしたら──。
次第に明らかになるのは、「語ること」自体に潜むずるさと、「酔うこと」で曖昧にされる本音の所在でした。
前の章を読む:
▶ 第10章:社会の無関心と「止められなかった責任」──誰もが問われる罪
はじめから読む:
▶ 第1章:序章──映画『赦し』の核心へと導く視点
「語ること」に潜む演出性──真実より“印象”を狙う言葉たち
本作『赦し』において、とりわけ印象深いのが、“語る”という行為の扱われ方です。証言台や取り調べ室、面会室といった場面では、人々が何かを吐き出し、あるいは押し隠しながら、言葉を選びます。それらの語りは、ただの事実の陳述ではありません。どこか演技めいていて、聞く側に“どう受け取られるか”を意識しているようにも見えました。
特に再審の場面で語られる「いじめ」の証言は、物証を欠いたまま、自供の印象によって構成されていました。弁護人の弁舌は、真実の掘り起こしというよりも、観客(裁判官を含む私たち)に対する情緒的アピールに近いものがあります。信じたいから信じる、信じさせたいから語る──その“演出性”に気づいたとき、裁判という場をどこか舞台装置のように感じさせられます。

“加害者”であることの自覚と曖昧な距離感
また、面会を申し出た克に対し、夏菜が「日程はそちらに合わせます」と返す場面には、彼女の心の距離感がにじみます。本来、赦しを求める立場の人間が伝えるべき言葉としては、少し物足りない。それは、彼女の中で自分を“加害者”として捉える意識が希薄であることの現れに見えました。
夏菜は、いまだ“被害者のポジション”にとどまり、殻の中で語り続けています。その未成熟さは、物語の中心にある“赦し”というテーマを静かに裏切っているようにも感じられました。語られる言葉が、時に自己弁護や印象操作に変わる瞬間、観客は赦しの成立そのものが揺らぐことを目の当たりにするのです。
“酔い”に託された逃避──弱さがにじむ吐露の場面
語りではなく“酔い”によって感情を解放する描写も、繰り返し登場します。克、澄子、弁護人──それぞれがお酒を通じて胸の内をこぼす場面は、感情の吐露として一見自然ですが、同時に逃避の手段としても機能しています。
酔って語ることで、現実の重みから一時的に離れ、自分の弱さや本音を曖昧にすることが可能になります。登場人物たちが“酔う”たびに、そこには弱さと誤魔化しの影がちらつくのです。酔って語ることと、醒めて語ること──どちらが“赦し”に向かう一歩なのか、その問いは観る者の胸に静かに落ちてきます。

語りと酔いに見る“弱さ”の投影──私たち自身の姿として
語ることで許されたい人々と、酔うことで逃れたい人々。
そのどちらも、観客の心にある“弱さのかたち”と重なって見えます。
私たちはしばしば、他者に向けて誠実でありたいと思いつつも、自らの立場や心の不安定さに押されて、言葉を選び、誤魔化し、演出を施します。それは映画の登場人物だけでなく、私たち自身にも当てはまることなのです。
この映画は、語る行為や酔う行為を通じて、赦しや向き合いを演出的に描くことで、人間の弱さやずるさを露わにします。形式としての言葉、感情の代替としての酒──それらが絡み合うことで、赦しの営みは一層複雑に、そして不確かなものとして浮かび上がるのです。

次章予告
次章では、「語ること」と「謝ること」の間に潜む微妙な心理を分析します。
形式だけが整えられた謝罪の場面──その沈黙が物語るのは、赦されたいのではなく“終わらせたい”という心の奥底です。
人が本当に向き合うべきものとは何か──静かに見つめる章になります。
次の章を読む:
▶ 第12章:形式の仮面──語られる謝罪、語られない本音