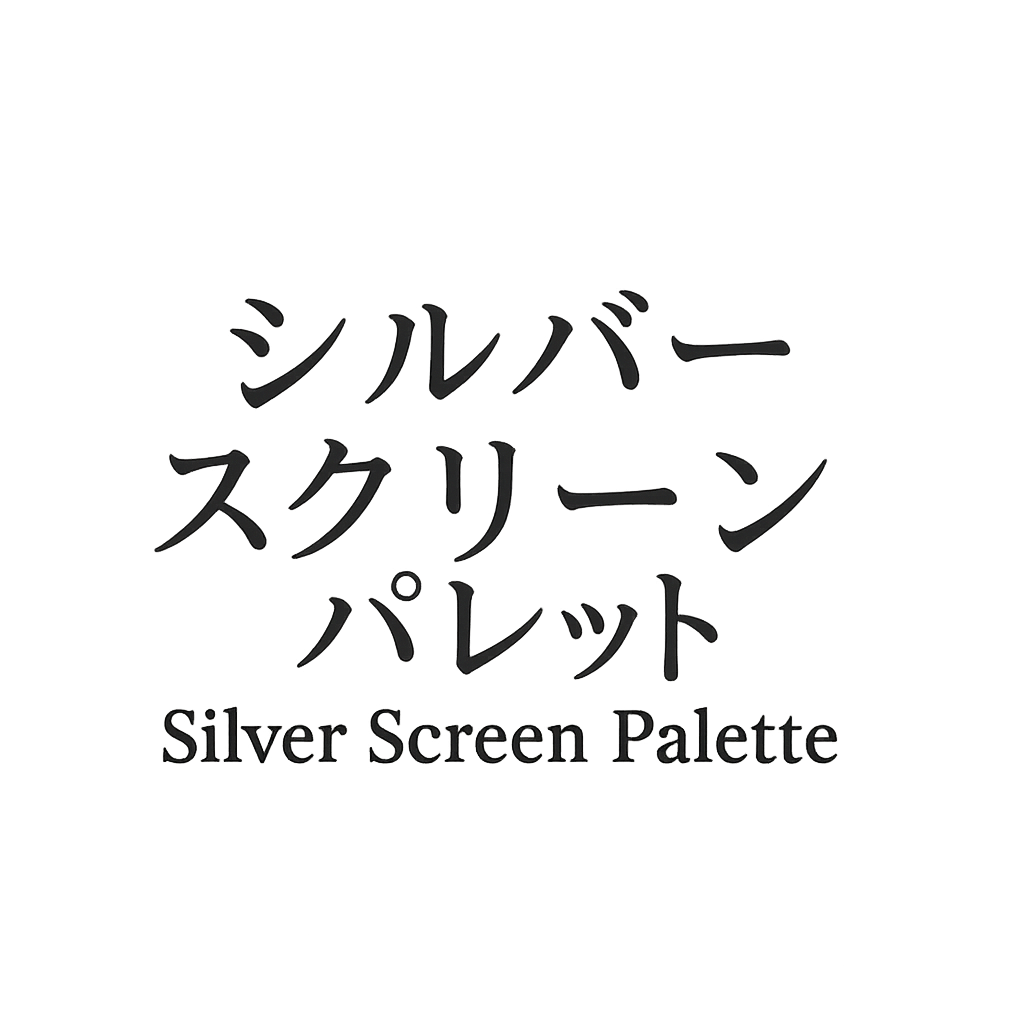映画 赦し レビュー 第13章:凍結された父性──“やり直し”に執着する理由【ネタバレ注意】

【ネタバレを含みます】
本記事では、映画『赦し』の登場人物や象徴的なシーンについて触れています。物語の印象を大切にされたい方は、鑑賞後にご覧いただくことをおすすめいたします。
出典:YouTube / A FILM BY ANSHUL CHAUHAN 公式チャンネル
第13章:凍結された父性──“やり直し”に執着する理由
人はなぜ、失われた関係に手を伸ばしてしまうのでしょうか。
それがもう戻らないと分かっていても、過去にすがりたくなる瞬間がある。
終盤、克の「やり直さないか」という問いかけには、そんな痛々しい未練と執着が滲んでいました。
前の章を読む:
▶ 第12章:形式の仮面──語られる謝罪、語られない本音
はじめから読む:
▶ 第1章:序章──映画『赦し』の核心へと導く視点

「父親だった自分」を維持するための呼びかけ
本作の終盤、克が澄子に「やり直さないか」と語りかける場面は、単なる再出発の誘いに見えながら、その言葉の奥にはもっと複雑で切実な動機が潜んでいるように思えます。
彼は本当に、元妻と人生をもう一度歩みたいと願っているのでしょうか。
それとも、彼が求めているのは、“父親だった自分”を維持するための拠り所に過ぎないのでしょうか。
澄子と共に過ごした時間は、娘の存在を中心にした「父と母」の時間でもありました。克にとってその時間は、父親としてのアイデンティティを保証してくれる唯一の証。だからこそ彼は、澄子にすがることで「父であれた過去」を現在に引き延ばそうとしているように見えるのです。

共に悲しんだ“証人”を失いたくないという執着
澄子はすでに新たな家族を持ち、「いまは家族がいる」と明確に一線を引いています。それでも克は、まるでその線を消そうとするかのように食い下がります。
この態度には、単に未練深い元夫という以上に、“喪失をまだ受け入れきれない男”の孤独と葛藤が浮かび上がっています。
澄子は「恵未の母」であるだけでなく、「娘を亡くした母」としての時間を克と共有した、唯一の“証人”でもあります。その彼女を完全に失うことは、克にとって「父親だった自分」をも失うことに直結します。
彼が澄子に「やり直さないか」と呼びかけるのは、愛情の再燃ではなく、“証人”をつなぎとめたいという渇望の表れでもあるのです。
つまり克は、「もう父親ではない」という現実に、どうしても折り合いをつけられずにいる。
喪失は彼にとって「出来事」ではなく、「いまも続く現在形」であり続けているのです。

「父親であれた時間」への固執──悲劇の現在形として
娘の死は、克にとって“過去を封じる悲劇”ではなく、“父親だった自分”を実感できる最後の手がかりでした。
そのため彼は、記憶を「温かな思い出」として昇華するのではなく、「悲劇の現在形」として持ち続けることを選んでしまいます。
澄子が新たな家庭を築き、前を向いて歩んでいることを知りながら再接近しようとする克の姿には、“取り残された者”の孤独と、他者が癒えていくことへの微かな嫉妬すらにじんでいます。
「喪失を抱えているのは自分だけだ」「自分こそが最も傷ついている」──その思い込みが、彼をますます“娘を亡くした父親”という役割に閉じ込めてしまうのです。
結果として、克は「父であった時間」を繰り返し反芻し、その痛みを凍結させることでしかアイデンティティを保てなくなっているように見えます。
前を向けない理由──「父性の喪失」という別れ
克の言動は、単なる未練や弱さではなく、「喪失の凍結」と「父親像の固定化」の表れといえるでしょう。
彼にとって前を向くことは、娘の死を受け入れること以上に、「父である自分」と決別することを意味してしまうからです。
“もう父親ではない自分”を受け入れること──それは、愛情の喪失だけでなく、「誰かの親であれた時間」への別れでもあります。
その別れは、伴侶を失うこととも、子を失うこととも異なる、極めて特異で深い痛みを伴うものです。克がそこから抜け出せないのは、彼の弱さというより、人間が持つ「役割への執着」の極端な形なのかもしれません。
結び──凍結された父性の悲哀
こうして見ると、克の「やり直さないか」という言葉は、澄子への愛情告白ではなく、“父親だった自分”を守るための最後の手段であったといえるでしょう。
彼の執着は滑稽でもあり、同時に深い哀しみの響きを持っています。
前を向くことよりも、過去にとどまることを選んだ彼の足元には、「父親であり続けるために悲劇を手放さない」という矛盾がひっそりと横たわっていました。
その姿は、父性という役割を失った人間がいかに生き延びようとするかを示す、痛切な鏡像のように感じられます。
次章予告
次章では、誰もが手探りのまま進む終幕の裁判に注目します。
形式に飲まれず、本質を見極めようとしたひとつの言葉──その小さな決断が灯した、“人間の正義”について考えます。
次の章を読む:
▶ 第14章:形式を断ち切る一言──ささやかな正義の灯