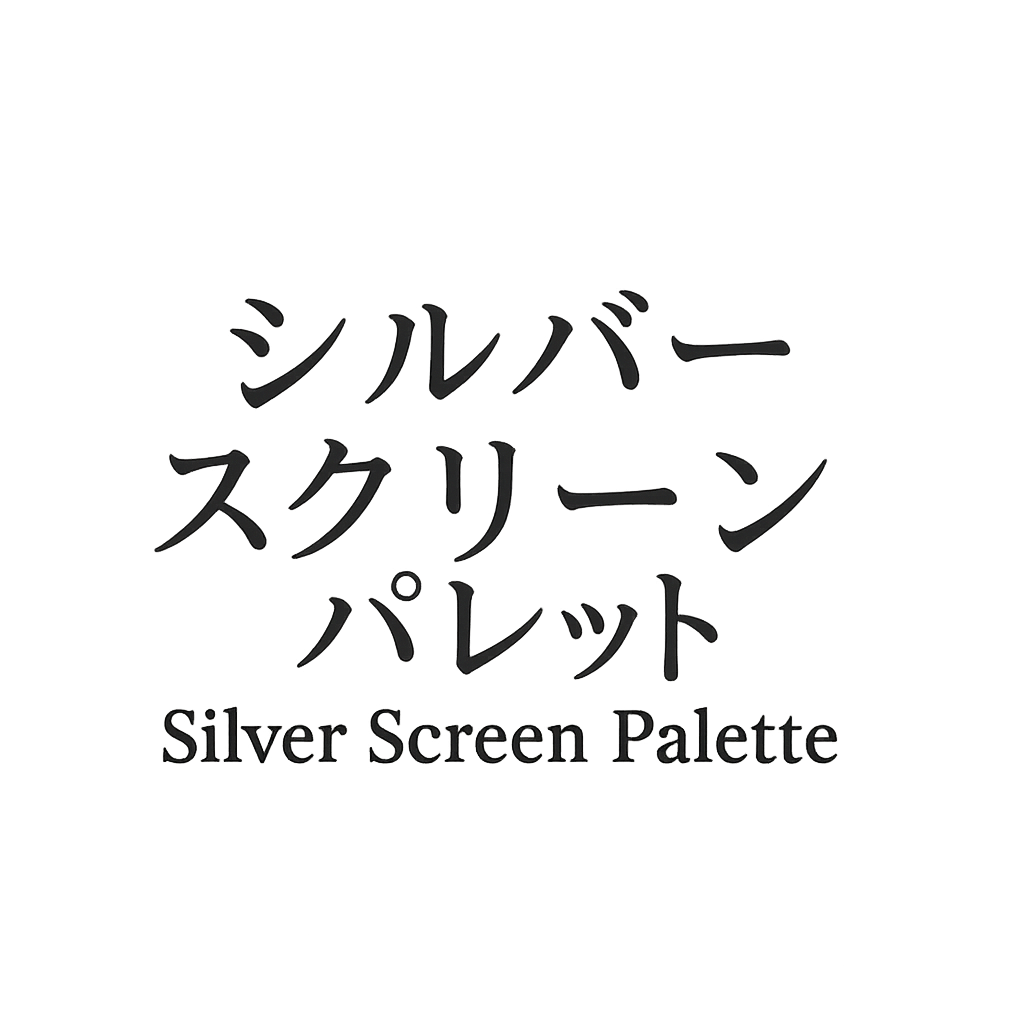映画『ゴールド・ボーイ』感想|舞台設定とストーリーの噛み合わない魅力

今この映画を見る理由
唯一無二の美しい自然を背景に、見かけと中身のズレが言葉以上に語りかけてくるような体験ができるのが本作の魅力だと思います。映像の美しさに惹かれながらも、「なぜこの場所だったのか」を考えることで、サスペンス映画の見方が鮮やかになる気がしました。
【ご一読ください】
本記事は、物語の核心部分には触れず、作品全体の空気感やテーマ性、鑑賞時の参考となる観点を中心に構成しています。
また、作品によっては、人間関係や社会的な題材、心理的な揺らぎを扱う場面が含まれることがあります。ご自身の感受性や鑑賞環境に応じて、無理のない形でお楽しみください。

総合まとめ
国内平均星評価:3.83/5
海外平均星評価:3.34/5
※このチャートは、確認できた国内外の評価サイトのスコアをもとに作成しています。
未評価のサイトは平均に含めていません。あくまで参考としてご覧ください。
あらすじ
(以下、公式サイトより引用)
それは完全犯罪のはずだった。まさか少年たちに目撃されていたとは…。
義父母を崖から突き落とす男の姿を偶然にもカメラでとらえた少年たち。事業家の婿養子である男は、ある目的のために犯行に及んだのだ。
一方、少年たちも複雑な家庭環境による貧困や、家族関係の問題を抱えていた。
「僕達の問題さ、みんなお金さえあれば解決しない?」
朝陽(13)は男を脅迫して大金を得ようと画策する。
「何をしたとしても14歳までは捕まらないよ。少年法で決まってるから」
殺人犯と少年たちの二転三転する駆け引きの末に待ち受ける結末とは……。
出典:映画『ゴールド・ボーイ』公式サイト
沖縄の美しい景色に彩られながらも、「なぜ沖縄だったのか」という疑問が残る――映画『ゴールド・ボーイ』は、壮観な風景と物語の間にあるズレがかえって観る者の好奇心を刺激するように感じました。

舞台と物語のズレが気になった
金子修介監督は中国原作を「日本社会に落とし込む場」として、沖縄を選んだと語っているようです。しかし実際には方言や地域の文化、社会的事情はほとんど描かれず、この設定にどれほど意味があったのかは疑問と感じました。崖から人を突き落とす冒頭の場面は地方であれば成立し、東京ではなくても、「崖のある土地」なら実現できたと思えました。沖縄の風景描写とストーリーのつながりは弱く、やや舞台が“借景”に終始している気にも思えました。
映像の美しさが物語を支えていない
沖縄の海や崖、光の差し込みなど映像面で魅せる瞬間は確かにあり、映像作品としての美的価値は感じました。とはいえ、その美しさがサスペンスのテンションやキャラクターの駆け引きには影響しないようにも思えました。美しい画があるのに、いざその背景にある緊張感や心理描写に結びつかないため、映像美が物語に機能しきれていないとも思いました。

登場人物と地域性の乖離
少年少女たちの家庭環境や性格描写も、沖縄固有の事情が反映されている感じはなく、普遍的なキャラクターとして描かれている印象でした。岡田将生さん演じる犯人についても、沖縄ならではの動機や社会背景は見えてこず、「どこでも起こりそうな事件」としてしか捉えられませんでした。米軍基地や地域の政治構造といった「大人と子ども」の対立構造が背景にあるのではないかという制作側の想定も、スクリーンからは読み取れず、物語の奥行きが惜しいとも感じました。
制作意図と描写とのギャップ
監督の意図には「映像美」「隔絶感」「地域社会の挿入」があったようですが、映画の中ではそれらが噛み合っていないようにも思えました。沖縄の美しさはあっても、それが物語を動かす駆動力にはなっておらず、舞台と描写が独立してしまっているように感じました。このギャップこそが、本作を観た後に強く残る印象だったように思います。

【次回予告】『ヴェノム:ザ・ラストダンス』
エディ・ブロックとヴェノムが、最強の敵・ヌルとゼノファージに挑む壮絶バトル。
劇場公開を経て、9月9日からAmazon Primeで配信中です。
宇宙規模の脅威と二人の絆の変化から目が離せない、シリーズファン必見の一作。
アクション映画好きも、今すぐ自宅でその興奮を体感できます。