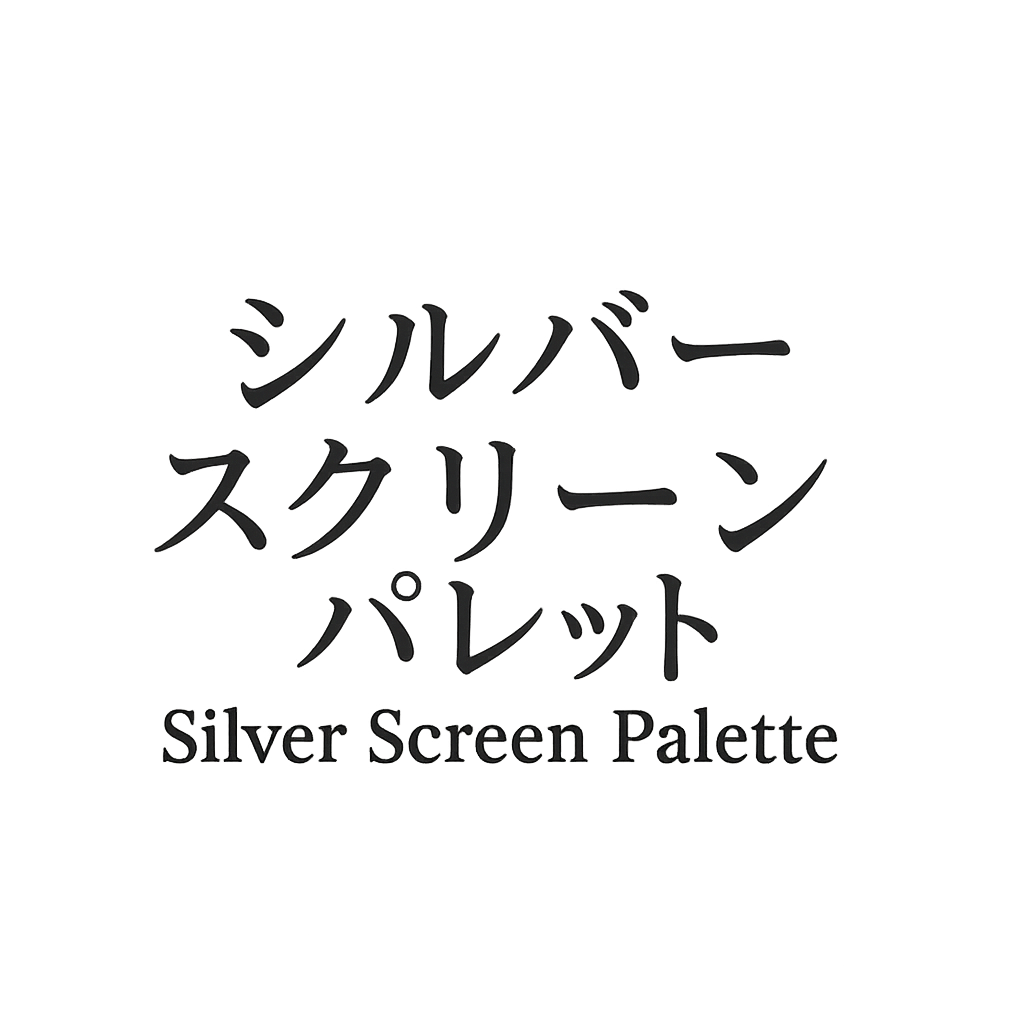COLUMN:なぜカナダが『The Order』を撮れたのか?――北米の隣人がアメリカの“闇”を映すとき

出典:The Order | Official Trailer | Prime Video
※本コラムには映画『The Order(2024)』の一部シーンに関する言及が含まれます。
ストーリーの核心的なネタバレは避けていますが、印象的なシーンや作品のテーマ解釈について触れています。
ご鑑賞前にまっさらな状態で楽しみたい方は、ご注意ください。
【ご注意ください】
本記事では、過去に実在した事件や、過激な思想と見なされている書籍について言及しています。これは、事実関係やその表現が社会に与えた影響を検証することを目的としたものであり、特定の思想、暴力行為、または過激な主張を肯定・推奨する意図は一切ありません。
『The Order』がカナダ映画だと知ったとき
『The Order』がカナダ映画だと知ったとき、正直少し驚きました。
描かれるのはアメリカの極右思想と暴力事件。舞台も登場人物もアメリカです。それなのに製作国はカナダ。「なぜカナダが?」という疑問が拭えませんでした。
しかし観終えてみると、カナダという“距離”があったからこそ、この映画は冷静に、鋭く、そして痛々しく暴力を見つめることができたのだと思えてきました。
アメリカと似て非なる国、カナダ
アメリカとカナダは地理的にも歴史的にも近い存在ですが、文化的な性格は大きく異なります。
銃規制、医療制度、国家観、多文化主義──どれをとってもアメリカとは対照的です。カナダでは「国家の強さ」よりも「他者との共存」が語られやすい印象があります。
こうした土壌があったからこそ、白人至上主義を外部から批評的に見つめる姿勢が取れたのでしょう。映画の語り口が冷徹で分析的なのも、当事者ではない立場から描いているからこそだと感じられました。

カナダ映画が持つ静かな胆力
カナダの映画産業は、派手さよりも社会的テーマへの深いアプローチで知られています。公共資金(NFBやTelefilm Canada)による支援があることで、商業的制約に縛られずに作られる作品が多いのです。
『The Order』のように「過激思想への批判」や「人間の暗部を見つめる作品」は、国際映画祭でも評価されやすいジャンルです。感情的な煽動ではなく、冷徹に問いを投げかける姿勢は、まさにカナダ映画らしさの表れだと思いました。

『The Order』はなぜ今、どこから生まれたのか?
アメリカ社会が生んだ暴力を、アメリカ自身が正面から描くのは難しいのかもしれません。感情の渦中にある者にとって、批評的距離を保つことは簡単ではないのです。
だからこそ、カナダという“隣国”からの視線が意味を持ったのだと思えます。映画の語り口には、「これはあなたたちの問題であり、私たちの問題でもある」という静かな共振が感じられました。
そして私たち観客に問いかけます。
「あなたの国では、これを撮れるだろうか? 語れるだろうか?」
この問いは映画を越えて、私たちの社会や言論の自由にまで及ぶように思えます。『The Order』は、カナダで作られたからこそ、この問いを静かに、しかし確実に投げかける力を持ち得たのだと思います。

作品をすでにご覧になった方へ
物語の核心に踏み込んだネタバレありの感想・考察記事も公開しています。
実在の事件や『ターナー日記』との関連を含め、映画がなぜ“今”作られたのか、その問いに迫りました。
❖ 『The Order(2024)』ネタバレあり感想・考察|実話が残した“終わらない戦慄”を観る
【次回予告】映画『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』静かに愛を求める人々の物語
静かな冬の夜に、胸の奥をそっと揺さぶる物語が待っています。
『ホールドオーバーズ 置いてけぼりのホリディ』は、孤独を抱えた三人が寄宿舎に残り、互いに心の傷を少しずつ溶かし合う温かなヒューマンストーリー。
愛をもらうことだけでなく、与えることの意味を問いかけるこの作品は、あなたの心にしみる“冬の贈り物”になるでしょう。
次回は、この静かな冬の物語に触れてみませんか?