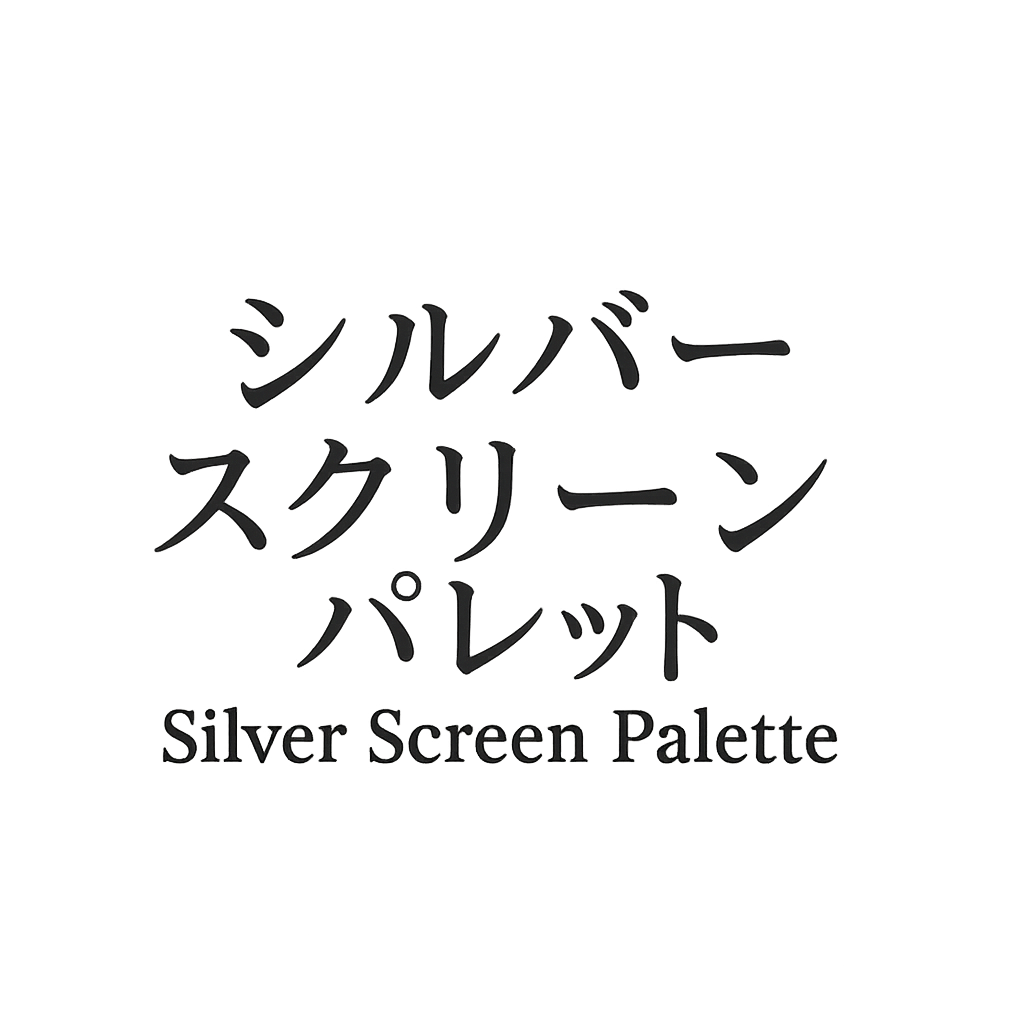映画 赦し レビュー 第9章:語られた言葉の空虚──形式と“赦し”のすれ違い【ネタバレ注意】

【ネタバレを含みます】
本記事では、映画『赦し』の登場人物や象徴的なシーンについて触れています。物語の印象を大切にされたい方は、鑑賞後にご覧いただくことをおすすめいたします。
出典:YouTube / A FILM BY ANSHUL CHAUHAN 公式チャンネル
第9章:語られた言葉の空虚──形式と“赦し”のすれ違いへ
どれほど慎重に選ばれた言葉であっても、そこに心が宿っていなければ、相手には何も届かないのかもしれません。映画『赦し』の面会室で交わされた澄子と夏菜の対話は、「語られること」と「伝わること」の決定的な隔たりを浮かび上がらせます。

一見誠実に見えるやりとりの中に潜む、赦しきれない違和感──それは、言葉という形式が感情を置き去りにする瞬間にこそ、最も強く滲み出るものなのだと感じさせられました。
前の章を読む:
▶第8章:沈黙の正義──支援を受けることへの偏見と父の存在意義
はじめから読む:
▶ 第1章:序章──映画『赦し』の核心へと導く視点
面会室の“丁寧すぎる”やりとりが示すもの
澄子が拘置所で夏菜と向き合う場面は、この物語の感情的な深層に静かに切り込んでいきます。娘を奪った加害者と、面と向かって言葉を交わすという、極限の場面。
しかし、ここでの対話は、不思議なまでに温度のない空気に包まれていました。
澄子が面会室に入った瞬間、夏菜が発した第一声は「どうぞお座りください」。一見すれば丁寧な言葉遣いです。けれどこの言葉が放つのは、礼儀や誠意よりも、むしろ感情を排した機械的な距離感でした。
欠けていたのは「赦しへの覚悟」
本来ならば、「お越しいただきありがとうございます」「お話をさせていただけることに感謝しています」といった、赦しを乞う者としての謙虚さが滲むはずの場面。それがまるで、役割を演じるかのような抑揚のないやりとりに終始してしまうのです。
夏菜の語る言葉には、“加害者としての反省”ではなく、“自身の過去にまつわる説明”が先行していました。確かに、その生い立ちや環境には社会的に見過ごせない背景もありました。けれど、それは「なぜ、あの命を奪ったのか」という問いに対する答えにはなっていないのです。
交わされない“心”と、すれ違う“赦し”
対話のように見えて、実際にはそれぞれが自分の視点をただ述べているだけ。ふたりの間には、言葉を通じての“心の往復”が決定的に欠けていました。

その場面に漂っていたのは、“赦される準備”を整えたかのように振る舞う夏菜と、“赦す”という感情に踏み込めない澄子との、すれ違いそのものでした。
形式的には会話が成立していても、実際には互いの心が触れ合うことはなく、空虚さだけが広がっていったのです。
形式化された言葉が生む空虚
どれほど敬語を用いようと、言葉に思いがこもっていなければ、それはただの「形式」にすぎません。そして形式ばかりが前に出るとき、そこに浮かび上がるのは、痛みを共有することの不可能性なのです。
この面会室の場面は、赦しという行為の成立に必要なのは「言葉そのもの」ではなく、「言葉の裏にあるもの」──つまり、感情や覚悟、そして相手と向き合おうとする真摯さなのだと静かに告げています。
誠意の欠如が遠ざける「赦し」
誠意が形式に変わるとき、対話はその機能を失い、「赦し」は遠ざかっていく。その冷ややかさが、かえって深く心に残るのです。
澄子にとって、夏菜の発する言葉は“赦しを求める声”ではなく、“自己を守るための説明”に過ぎなかったのかもしれません。だからこそ、彼女の心は動かなかった。
形式がどれほど整っていても、そこに心が伴わなければ、赦しという営みは生まれない──この静かな面会室の沈黙は、そんな痛切な真実を私たちに突きつけているのかもしれません。

次章予告
次章では、“何も言わなかった”人々の静けさに耳を澄ませます。
大人たちが見て見ぬふりをした結果、悲劇は避けられなかった──
もし、あのとき誰かが声をかけていたなら──
「止められなかった責任」とは何か。映画『赦し』が突きつける、社会全体が抱える“沈黙の罪”を見つめていきます。
次の章を読む:
▶ 第10章:社会の無関心と「止められなかった責任」──誰もが問われる罪へ